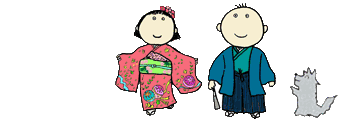- ホーム >
- 民族・地域一覧[みんぞく・ちいきいちらん] >
- 日本[にっぽん] >
- 陵王[りょうおう]の装束[しょうぞく]
日本[にっぽん]
陵王[りょうおう]の装束[しょうぞく]
-
◆装束[しょうぞく]ってなんのこと?
舞[ま]う人[ひと]の服[ふく]や冠[かんむり]や手に持[も]つもののこと。
ひとりでは着[き]られないから、ほかの人[ひと]が手伝[てつだ]ってあげるんだ。 -
◆「陵王[りょうおう]」はどんな舞楽[ぶがく]なの?
むかし、中国[ちゅうごく]に北斉[ほくせい]という国[くに]があったころ。王様[おうさま]に、蘭陵王[らんりょうおう]という弟[おとうと]がいた。陵王[りょうおう]ともよばれた。あるとき、となりの国[くに]とたたかって北斉にもどると、仮面[かめん]をつけていた陵王は敵[てき]かも?!とおもわれて城[しろ]に入れない。そこで仮面をとると、北斉の兵隊[へいたい]はよろこんでむかえ入[い]れた。そして、「蘭陵王入陣曲(らんりょうおう・にゅうじんきょく)」を歌って、勇敢[ゆうかん]な蘭陵王をたたえたんだって。
あとになって、蘭陵王はきれいだったから、敵[てき]から弱虫[よわむし]だと思[おも]われないために、お面[めん]で顔をかくして戦ったという話[はなし]が広[ひろ]まったんだって。
舞楽の「陵王」にも、すてきに強[つよ]い蘭陵王がみえるとおもうよ。
-
◆舞楽「陵王」の装束はこれだけ
-
①差貫[さしぬき]
袴[はかま]のこと。
裾[すそ]を足首[あしくび]にひもでくくりつけるよ。
-
②袍[ほう]
袍[ほう]は、昔[むかし]、身分[みぶん]のたかい人[ひと]が着[き]た上着[うわぎ]。
とっても裾[そす]が長[なが]いんだ!画像[がぞう]の左側[ひだりがわ]が袍[ほう]だよ。
袴[はかま]のこと。
裾[すそ]を足首[あしくび]にひもでくくりつけるよ。
-
③裲襠[りょうとう]
裲襠[りょうとう]は、袍の上[うえ]に着[き]る服[ふく]。
刺繍[ししゅう]がとっても豪華[ごうか]なんだ。ふちには毛縁(けべり)というフサフサの飾[かざ]りが、グルっとついているよ。

-
④面[めん]
眼[め]を見[み]開[ひら]いて、大[おお]きな口[くち]をあけているね。
頭[あたま]には龍[りゅう]もしくは金翅鳥[こんじしちよう]を乗[の]せているんだ!
-
⑤牟子[むし]
頭[あたま]をかくす布[ぬの]。防災頭巾[ぼうさいずきん]みたいな形[かたち]。

-
⑥桴[ばち]
舞[ま]うときに手[て]に持[も]つ棒[ぼう]。

-
-
◆舞楽[ぶがく]「陵王[りょうおう]」の舞[まい]の所作[しょさ]を見[み]てみよう
舞[まい]の中[なか]に出[で]てくる所作[しょさ]が描[えが]かれた絵画作品[かいがさくひん]もあるよ。
ここでは、5つの作品[さくひん]を紹介[しょうかい]するよ。
「陵王[りょうおう]」のポーズ、真似[まね]してみたくなっちゃうね!-

①土佐光信 伝原作「舞楽屏風」模本作品〈部分〉
-

②山田於莵三郎「徳川式室内装飾」〈部分〉
-

③小堀鞆音「蘭陵王」〈部分〉
-

④千頭庸哉「陵王」〈部分〉
-

⑤「公事絵言葉 乾」模本作品〈部分〉
■「舞楽[ぶがく]「陵王[りょうおう]」装束[しょうぞく]の着付[きつけ]」に使用[しよう]
①竹内久一[たけうちひさかず]「陵王面[りょうおうめん]」1911年[ねん]
②「陵王装束[りょうおうしょうぞく]」明治時代[めいじじだい]
■「舞楽[ぶがく]「陵王[りょうおう]」の舞[まい]の所作[しょさ]」に使用[しよう]
①土佐光信[とさみつのぶ] 伝[でん]原作[げんさく]「舞楽屏風[ぶがくびょうぶ]」模本作品[もほんさくひん]、制作年[せいさくねん]・作者不詳[さくしゃふしょう]〈部分[ぶぶん]〉
②山田於莵三郎[やまだおとさぶろう]「徳川式室内装飾[とくがわしきしつないそうしょく]」1893年[ねん]
③小堀鞆音[こぼりともと]「蘭陵王[らんりょうおう]」制作年不詳[せいさくねんふしょう] 〈部分[ぶぶん]〉
④千頭庸哉[ちかみようさい]「陵王[りょうおう]」(含花育英帖[がんかいくえいちょう]より)制作年不詳[せいさくねんふしょう]〈部分[ぶぶん]〉
⑤「公事絵言葉[くじえことば] 乾[けん]」模本作品[もほんさくひん]、制作年[せいさくねん]・作者不詳[さくしゃふしょう]〈部分[ぶぶん]〉
-